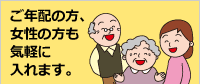巻き肩

こんなお悩みはありませんか?

巻き肩の悩み 5つ
筋肉のバランスの乱れ: 巻き肩の主な原因の一つは、肩の前後左右の筋肉バランスが悪くなることです。特に、胸部の筋肉が強くなりすぎて、背中の筋肉が弱くなることで、肩が前に出てしまいます
悪姿勢による影響: スマートフォンやパソコンを長時間使用することで、前傾姿勢が続き、肩が前に出やすくなります。この姿勢が続くと、巻き肩が悪化する可能性があります
骨盤の歪み: 骨盤の歪みも巻き肩の原因となることがあります。骨盤が歪むことで、体全体の姿勢が崩れ、肩の位置にも影響を与えます
筋力低下: 年齢や運動不足により、肩周りの筋力が低下すると、肩を正しい位置に保つことが難しくなり、巻き肩が進行します
生まれつきの骨格: 一部の人は、生まれつきの骨格によって巻き肩になりやすい場合があります。この場合、遺伝的要因が影響していることがあります
巻き肩は、姿勢や筋肉のバランスに大きく影響されるため、日常生活の中で意識的に改善することが重要です。ストレッチや筋力トレーニングを取り入れることで、巻き肩の悩みを軽減することが可能です。健康的な姿勢を保つために、日々の生活習慣を見直してみましょう。
巻き肩について知っておくべきこと

巻き肩の原因と対策について
筋肉のバランスの乱れ
巻き肩の主な原因の一つとして、肩の前後左右の筋肉バランスの乱れが挙げられます。特に、胸部の筋肉が緊張しやすく、背中の筋肉が弱くなることで、肩が前方に引っ張られやすくなります。
悪姿勢による影響
スマートフォンやパソコンを長時間使用することで前傾姿勢が続くと、肩が前に出やすくなります。このような姿勢が習慣化することで、巻き肩の症状が進行する可能性があります。
骨盤のゆがみ
骨盤のゆがみも巻き肩に関係することがあります。骨盤の位置が崩れると、全身のバランスが乱れ、肩の位置にも影響を及ぼすことがあります。
筋力の低下
加齢や運動不足により肩周りの筋力が低下すると、肩を正しい位置に保ちにくくなり、巻き肩の状態が続いてしまうことがあります。
巻き肩は、姿勢や筋肉バランスの影響を受けやすいため、日常生活の中で意識的にケアを行うことが大切です。
ストレッチや筋力トレーニングを取り入れることで、巻き肩のお悩みの軽減が期待できます。健康的な姿勢を保つために、まずは日々の生活習慣を見直すことから始めてみましょう。
症状の現れ方は?

巻き肩によって現れる主な症状について
巻き肩とは、肩が前方に丸まった状態の姿勢を指し、日常生活の中で気づかないうちにさまざまな不調を引き起こすことがあります。以下に、巻き肩に関連すると考えられる代表的な症状をまとめました。
巻き肩の主な症状
肩こり
肩周りの筋肉が常に緊張した状態になりやすく、慢性的な肩こりを感じることがあります。
頭痛
肩甲骨周辺の筋肉が硬くなることで血行が悪くなり、頭痛の症状が出ることがあります。
背中の痛み
巻き肩により背中の筋肉にも負担がかかり、張り感や痛みを感じることがあります。
呼吸の浅さ
胸郭の動きが制限されることにより、呼吸が浅くなり、息苦しさを感じることがあります。
全身の倦怠感
巻き肩による姿勢の乱れが自律神経のバランスに影響を与え、疲れやすさやだるさを感じることがあります。
吐き気
自律神経の乱れが原因で、まれに吐き気を伴うこともあります。
巻き肩の症状は、放置すると日常生活に支障をきたす可能性があります。早めにケアを始めることで、こうした不調の軽減が期待できます。
ご不安なことがあれば、ぜひ当院にご相談ください。
その他の原因は?

巻き肩の主な原因とは?
巻き肩は、現代人に多く見られる姿勢の崩れであり、さまざまな要因が関係しています。以下に、巻き肩を引き起こす主な原因をまとめました。
姿勢の乱れ
長時間のデスクワークやスマートフォンの使用により、前かがみの姿勢が続くことで胸部の筋肉が縮み、肩甲骨が前方に引き寄せられやすくなります。
骨盤の傾き
骨盤が前後に傾いてしまうと、背骨のカーブが乱れ、猫背のような姿勢を取りやすくなります。その結果、肩関節も内側に巻き込まれやすくなります。
筋肉の緊張と柔軟性の低下
肩や首まわりの筋肉が緊張し、柔軟性が低下することで、肩の可動域が狭まり、巻き肩の状態が助長されることがあります。
寝る姿勢の影響
横向きで寝る習慣があると、肩に体重がかかりやすく、無意識に肩を前に引き寄せるような姿勢になりやすくなります。
これらの要因が重なることで、巻き肩が進行する可能性があります。日常の姿勢を見直し、適切な施術やセルフケアを取り入れることで、巻き肩の軽減が期待できます。気になる方は、早めのご相談をおすすめいたします。
巻き肩を放置するとどうなる?

巻き肩が引き起こす身体の不調
巻き肩になると、さまざまな身体の不調が現れることがあります。主な症状は以下の通りです。
肩や首のこり
巻き肩の状態では、首から肩にかけての筋肉が緊張しやすく、筋肉の柔軟性も失われるため、慢性的な肩こりや首こりを感じることが多くなります。
頭痛やストレートネックのリスク
筋肉が硬くなることで血流が悪くなり、頭痛を引き起こすことがあります。また、頸椎の正常なカーブが失われてしまい、ストレートネックと呼ばれる状態になる場合もあります。
呼吸の浅さ
肋骨の動きが制限されることで呼吸が浅くなり、体に取り込む酸素の量が減ってしまいます。これにより、疲れやすさや集中力の低下を感じることもあります。
巻き肩を放置するとこれらの不調が悪化する恐れがありますので、早めのケアや施術が大切です。気になる症状がある方は、ぜひ当院へご相談ください。
当院の施術方法について

巻き肩の施術について
巻き肩とは、肩甲骨が前方に突き出し、肩が内側に巻き込まれた姿勢のことを指します。この状態になると、肩や首の痛み、肩こり、頭痛などの不調が現れることがあります。
巻き肩の主な原因
姿勢の悪さ
長時間のデスクワークやスマートフォンの使用により、胸の筋肉が縮み、肩甲骨が前方に引っ張られてしまいます。
筋肉バランスの崩れ
胸の筋肉が過剰に発達し、背中の筋肉が弱くなることで、肩甲骨が前に引っ張られやすくなります。
筋肉の柔軟性低下
肩周りの筋肉の柔軟性が低下していることも、巻き肩の原因の一つです。
これらの原因に対して、当院では一人ひとりの状態に合わせた施術を行い、筋肉のバランスを整え、柔軟性を高めることで巻き肩の改善を目指します。具体的には、ストレッチや筋力強化、姿勢矯正などの方法を組み合わせて対応しております。
お悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。
軽減していく上でのポイント

巻き肩改善のためのポイント
正しい姿勢を意識する
座り姿勢:お尻を背もたれにつけ、頭から背中までをまっすぐに保ちましょう。胸を開き、顔は正面を向くことが大切です。
スマホの持ち方:スマホは胸元ではなく顔の高さで持ち、視線を正面に保つことで前かがみの姿勢を防げます。
ストレッチを行う
肩回し:両手を肩に添え、肘で大きな円を描くように内回し・外回しをそれぞれ10回行いましょう。
深呼吸ストレッチ:両手を頭の後ろで組み、肘を外側に広げながら深呼吸をします。胸をしっかり開くことができます。
筋力トレーニング
肩甲骨を引き寄せる運動:背筋を伸ばし、両手を背中に回して手のひらを合わせ、肩甲骨を寄せるように持ち上げる動きを数回繰り返しましょう。
適度に休憩を取る
同じ姿勢が続くと筋肉が硬くなりやすいので、定期的に立ち上がって肩や首のストレッチを行いましょう。
矯正サポーターの活用
長時間のパソコン作業時などに巻き肩防止のために矯正サポーターを使うのも効果的ですが、使い過ぎには注意が必要です。
監修

服部天神駅前接骨院 院長
資格:柔道整復師
出身地:熊本県熊本市
趣味・特技:身体を動かすこと